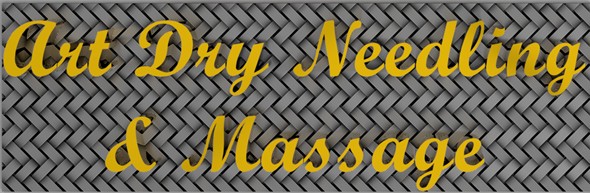コリの正体と生成原因・メカニズム
肩こりや首こりで悩んでいらっしゃる方は大変多いですが、「コリ」は、刺激する場所を間違えず丁寧に施術を行っていけば、ほぼ確実に柔らかくすることができます。この、ほぐれて痛みが軽減除去される場面についてはコリによる痛み専門の治療院、ドライニードリングvs.ウェットニードリングなどで述べているのでそちらをご参照ください。
ではその「コリ」とはそもそもどのようなものなのでしょうか?何が原因で、どのようにできていくのでしょうか?
コリの正体、生成の原因、メカニズムなどを見ていきます。
総論
コリがなぜできるのか?どのような状態なのか?
については日本でも欧米でも盛んに研究されています。
それらをまとめると、
コリは、その個人の回復限度を超えた過使用、あるいは全く使わない廃用、冷え、…などの理由で筋肉内・筋肉周囲の虚血(血行不良)→エネルギー不足が生じ、
筋肉(筋線維=筋肉細胞のこと)が収縮したままロックがかかってしまった状態
ということができます。
人の細胞のエネルギー源: ATP
人体には数十兆の細胞があると言われますが、それらの各細胞は何をエネルギーとして活動しているかというと、ATP(アデノシン3リン酸)です。
*食べ物には俗に“カロリー”と言われるエネルギーが含まれていますが、食べた物の“カロリー”が即、体で使われるわけではありません。ATPという種のエネルギーに変換されてはじめて人体の細胞で使える形になります。
ATPは、よくお金(通貨)に例えられますが筋肉細胞を含めたすべての細胞に共通のエネルギー源です。 車で言えばガソリン、電車ならば電気に相当します。
そしてこのATPは細胞内のミトコンドリアによって作られますが、その際、酸素が必要とされます。そして酸素はもちろん血液によって運ばれます。
要するに、血液が酸素をミトコンドリアに届けることができてはじめて各細胞はATP(エネルギー)を生み出すことができます。
したがって、何らかの理由で血行不良が生じると、酸素が届かず、ATPも作られずエネルギーが枯渇し、筋肉が収縮したままロックがかかって固まった状態となりそれが俗にコリと呼ばれます。
イメージ
fig.1) ↓これは、大腿四頭筋のコリの部分をエコー画像で記録したものです。(もっとも、エコー画像では筋肉は黒く抜けた画像として表出されますので、コリそのものは見えません。エコーで映るのは筋膜(筋線維の束である筋束を包んでいる膜)です。凝った筋肉を包む筋膜は正常なそれよりも白く厚く映りますので触診と併せて判断しています。

fig.2) 解説: 触診すると、赤丸のところでボコン、ボコン、と塊になっていてコリがあることが分かります。

(外側広筋:短軸断面 )
fig.3) 大腿四頭筋(外側広筋): fig.1,fig.2 に該当する部分
(『Atlas of Human Anatomy 』, third edition p474図を改変)

fig.4 ) (大腿部の断面): fig.1,fig.2 に該当する部分。fig.3 部位の拡大。
(『Atlas of Human Anatomy 』, third edition p487図を改変

ご存じの通り、かつお節は「かつおの筋肉」が乾燥して固まったものですが、ひどい凝りは「かつお節」みたいな状態をイメージしていただけば良いと思います。
また、実際はこるといっても特定の筋肉全体が塊になるわけではなく一部がかたまってこりになるのがほとんどです。例: 僧帽筋が凝るといっても僧帽筋全体ではなくその一部(例:筋束と呼ばれるレベル)が固まってコリになる。
筋肉の収縮とは?
筋肉が収縮する時は、まず細胞膜から活動電位が発生し、それが引き金となり筋小胞体という小器官からカルシウムイオンが放出され、太いフィラメントの間に細いフィラメントが滑り込みます。間に滑り込むことでお互いの距離が縮み筋肉の長さが短くなります = 筋収縮
つまり、脳からの命令が運動神経を通って筋肉に伝わり、最終的にカルシウムイオンが引き金となり筋収縮が起こります。

(出典: 『シンプル生理学』貴邑ほか, p.33)

(出典: 『シンプル生理学』貴邑ほか, p.34)
筋肉の血行不良を引き起こす原因となりうるもの
たとえ①弱い力でも入りっぱなしが長時間に渡れば過使用になる可能性がありますし、②短時間であっても通常の筋肉の能力を超えた強い力を出す場合、②-2. 特にそれが遠心性収縮(力が入ったまま筋肉が引き延ばされるような動き)である場合などが血行不良を引き起こす過使用の典型例です。
①長時間の弱い力による過使用:
移動時に荷物を持ち続けている、デスクワークなどでずっとうつ向いたままの姿勢でいるなどが挙げられます。荷物や頭の重さを支え続けるために力を出し続けることになります。
動きのない姿勢は、筋肉の収縮・弛緩のポンプ作用による血液還流がないままなので余計にダメージがひどくなります。物を配送する仕事の方よりもタクシーの運転手、デスクワークのような座業の方のほうがひどい腰痛になりやすいという報告もあります。椅子に完全に寄りかかり切りでない限り腰背部の筋肉に力が入り続けているので血行不良がひどくなりやすいことが一因と考えられます。歩き回るよりも動きの少ない立ち仕事がつらいのも同様の理由です。
また、精神的ストレス・緊張で無意識に筋緊張のレベルが高い状態が続く場合も同じです。
筋肉の基本的な機能・構造と作用でご紹介したように筋肉は(ex.上腕二頭筋)数千本の筋肉繊維(=筋肉細胞)で構成されており、その一本一本の線維に毛細血管が張り巡らされて絶えず酸素をはじめとする栄養・老廃物の運搬を行っています。筋肉に少しでも力が入ると筋線維が毛細血管を絞る状態となります。個体で例えれば首を絞められて息が出来ない状態と同じことです。
②強い力の過使用:
とても重いものを持ったり、普段使わない筋肉をしっかり使うような作業が該当します。
②-2. 遠心性収縮の例としては持った物を下ろす動作や、山や階段、坂道を下るような動きが典型例です。通常の歩行動作でも前脛骨筋(有名な足三里のツボがある筋肉)などは遠心性収縮を頻繁に行うのでたいていの人でコリが触知されます。(もし前脛骨筋に力を入れずに歩くと前に出した足のかかとが地面についた後、足底がパタンと地面にぶつかるような歩き方になります。)足三里は、指圧やマッサージ、鍼の刺激により強く響くことで有名ですが、強い響きが出るのは通常使用でもコリが溜まりやすい部位であることが一因と考えられます。
遠心性収縮がなぜ筋肉に大きな負担をかけるかと言いますと、このような場面においては関与する筋線維の数を減らされるので、働いている個々の筋線維からすると極めて大きな力を発揮しながら無理やりに引き延ばされている状態になるためです。
筋肉が凝った: 筋肉が収縮したままロックがかかった状態とは?
筋収縮は、ミクロレベルではミオシンという分子の頭部が、アクチンという分子に結合した状態を意味します。
生物の細胞のエネルギーは上記の通り、ATP(アデノシン3リン酸)です。
ミトコンドリアという細胞小器官がATPを産生していますがそのためには酸素が必要で、酸素を運んでいるのが血液です。
つまり、細胞が活動するのに必要なATPをミトコンドリアが作るためには酸素が血液から供給されないといけません。
意外に聞こえるかもしれませんが、収縮時のみならず、筋肉は弛緩するときにもエネルギーが必要です。
筋収縮のスイッチが入るにはカルシウムが必要ですが、今度、弛緩するときにはこのカルシウムが除去される必要があります。
カルシウムは放っておいて勝手に無くなる訳ではないのでエネルギー(ATP)を使って回収することが必要(カルシウム回収の場面)で、さらにアクチンとミオシンの結合がくっつきっぱなしにならずに離れさせるため(結合を解く場面)にもATPが必要になります。つまりATPというエネルギーがあって初めて筋肉(筋節)のロックが外れ弛緩できます。
カルシウムイオンを除去する能力には個体による遺伝子レベルでの差があるのでそれが同じことをしていても凝りにくい人と凝りやすい人が出る一つの原因と考えられます。詳しくは凝りやすい体質についてをご参照ください。
ちなみに、死後硬直も(血行不良というか血行ゼロ)によるエネルギー(ATP)不足で生じます。あえてキャッチーな表現をすれば、程度の悪いコリは生きながらにして死後硬直、のような状態です。
通常、臨床的には正常な柔らかい筋肉はお刺身のような適度の弾力を伴いつつもフワッとした感触ですが、硬くなった筋肉は消しゴムみたいな感触です。
少々極端な例ですが、かつお節のような状態がイメージしやすいかもしれません。かつお節はご存じの通り、魚の「筋肉」をカチカチになるまで乾燥させたものです。
<筋組織の酸素飽和度>

⇩ Palpable border of the induration
(筋硬結の触知可能な境界線)
– – – – – Normal mean pO2
(平均酸素濃度)
単位: 横軸 (mm)
縦軸(mm of Hg)
* 赤で囲まれた範囲は深刻な酸素欠乏状態ににあることを示す。
(Zeitschrift fur Rheumatologie 49:208-216)
筋線維の様子 (正常な筋線維 と 凝った筋線維)
< 正常な筋線維 >
fig.5 ) : 均一な太さの筋線維が並び、それぞれの筋線維を構成するサルコメア(縦に走る縞模様)もほぼ等間隔で規則正しく並んでいます。

< 凝った筋線維 1>
fig. 6)

こちらは、まず筋線維の太さがそれぞれ異なり、いびつな形をしているのが分かります。
そして、濃く黒く見える部位があるのはサルコメアの間隔がとても短くなっているためです。
「…The striations indicate severe contracture of the approximately 100 sarcomeres in the knot section of the muscle fiber…」
⇒ 中央の黒く見える部分にはおよそ100のサルコメアが凝集していると説明されています。
「The sarcomeres on both sides of the knots show compensatory elongation compared with the normally spaced sarcomeres in the muscle fibers running across the bottom of the figure…」
⇒ そして、その黒く見える部位の両脇は代償的に引き延ばされてサルコメアの間隔が通常よりも長くなっていると説明されています。
Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Third Edition, p30
(Travell, Simons& Simons)
fig. 7 )

(真ん中に100ほどのサルコメアが凝集され、その両端は代償的に引き延ばされサルコメアの間が広く空いている。)
* 中央やや下で水平に走る太い白線は肥厚した筋内膜と思われる。
< 凝った筋線維 2 断面図 >
fig. 8 )

Giant round muscle fiber in the center of the figure is surrounded by open space that may have resulted from a local sever enegy crisis. This space may contain substances that sensitize adjacent nociceptive nerve fibers.
⇒ 真ん中の太い筋線維を囲む白い組織(肥厚した筋膜のこと)は局所的・深刻なエネルギー枯渇の結果生じたもので、周囲の痛みを感じさせる侵害受容神経線維を敏感にさせる物質を含んでいる(意訳)。
In addition to the normal-size irregularly shaped muscle fibers surrounding the girant fiber, there are four abnormally small fibers…that may be the segments of muscle fibers which are narrowed because of contraction knot elsewhere in that fiber.
⇒ 太い筋線維の周囲に4つほど、異常に小さな(細くなった)筋線維があるが、おそらく太くなった筋線維のせいでそうなったと考えられる(意訳)。
* < 凝った筋線維1 >を見ると肥厚した筋線維の隣の筋線維は押しつぶされたように細くなってしまっていることと対応しています。
fig. 9 ) ↓ これらの状態を分かりやすく示したイラストがあります。

Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Third Edition, p95
(Travell, Simons& Simons)
Contracture knot がたくさん集まったものが臨床の現場で触知されるコリ ( 図の Nodule) です。
先に紹介した大腿四頭筋の索状の筋硬結(fig.1 ・fig.2 )はこの図の Taut band (の断面図)に相当します。
補足
血行不良・酸欠が起こるとどうなる?
血行不良で虚血状態(=酸欠・栄養不足)になると、筋肉組織は正常な状態を維持できなくなるので損傷され炎症が生じます。慢性炎症、くすぶり炎などと言われることもあります。(詳細は血行不良はなぜ悪いのかをご参照ください。)
病理組織学的所見によれば、このような凝った筋肉の周囲では炎症物質であるヒスタミン・血小板などの増加、ブラジキニン、プロスタグランジン、ヒスタミン、カリウムイオン、セロトニン、サブスタンスPなどの発痛物質の蓄積が認められます。組織はHp低下、つまり酸性になります。また、組成結合組織(筋膜)が厚く硬くなります。
炎症物質や痛み物質により痛覚線維が興奮すると血管収縮反射が生じ血流がさらに阻害されます。そして血流が阻害されるとATPの産生が減少しさらにエネルギー不足に陥り…と悪循環に陥ります。自己解決できない状態になっています。
筋筋膜性腰痛症(MPS)- 肩こりや腰痛との関係
ポリモーダル受容器の説明の所でご紹介しましたように、このような化学物質・炎症物質にさらされるとポリモーダル受容器は敏感になってきますから肩こり・首こり・腰痛…のように「痛く」なってくるのです。そして指で押されたり、鍼が当たると響きや痛みが出ることになります。(詳しくは鍼は痛いのか?-上手・下手との関係をご参照ください。)
”炎症”について – 炎症は悪?
ところで、「炎症」そのものは医学的には悪ではありません。組織が損傷した時には炎症反応がスムーズに進むことで治癒することができるのです。鍼やマッサージでコリが解消できるのもポリモーダル受容器が刺激されて神経性炎症という治癒の過程が始まるからです。(詳しくはポリモーダル受容器とはどのようなものか?をご参照ください。)
そして、治療後に痛み(筋肉痛)が出ることが悪いことではないことも、それが神経性炎症(という治癒過程)によるものであることから説明できます。(詳しくは鍼灸マッサージの治療後の筋肉痛をご参照ください。)
しかし、何らかの理由で炎症過程が治癒に至らず、途中で止まってしまっていれば慢性炎症であり、これは悪です。
コリとは、虚血によりこのような慢性炎症に陥った状態です。
コリを取る、とは、手指や鍼を使用してポリモーダル受容器を刺激することで、この慢性炎症を、いったん急性炎症の状態に引き戻して正常な治癒のルートに乗せるという作業です。したがって、マッサージ治療と鍼治療との間に質的な違いはありません。
参考)
『 Travell & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction 』 David Simons, 2018.
『シンプル生理学』(改訂第7版)貴邑冨久子, 根来英雄, 南江堂, 2018.
痛みとハリ治療, 日良自律4号1(93)一, 滋賀医科大学第一生理 , 横田敏勝.
『筋肉学入門 : ヒトはなぜトレーニングが必要なのか?』 石井直方, 講談社, 2009.