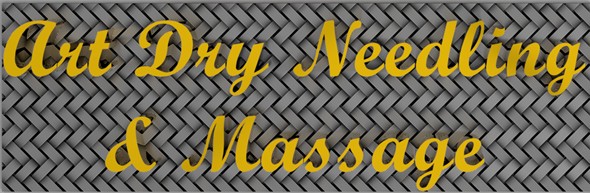下肢の治療(足のだるさ、股関節・膝関節痛、足をつる)
全身の筋肉の6~7割を下半身の筋肉が占めます。
当院への来院目的の上位は首・肩・腰の痛み、トラブルが占めているので当サイトにおいても上半身の治療に対する記述が多くなりますが、”足腰”の重要性は今さら指摘するまでもありません。
コリや痛みに対する治療として、当院では基本的に痛みの部位に近い所から治療していく方針をとっているので、例えば主訴が首の痛みの場合、首や肩、頭などから治療を始めていきます。
主訴である首そのものの痛みはたいていこれで問題なくなるはずですが、もし完璧を求めるとすれば頭を支えている首をさらに支える背中、その背中を支える腰 . . .腰を支える臀部 . . . 太もも… ふくらはぎ . . . 足の裏のように治療を進めていくことになります。定期的に治療に通ってくださる患者様にはこういったアプローチ(主訴+それより下位の部位を組み合わせた治療)をとることが多いです。
このように、現実的な意味においても比喩的な意味においても、足腰は身体の基礎の部分を成す部位ですし、近年のマイオカインの発見とそれに続く研究からも益々、下肢の重要性についての理解は深まっています(☞ 鍼の刺激によるマイオカイン分泌の可能性について)。
下肢のだるさ
大腿部でだるさを感じる場合、
主に
①大腿筋膜張筋、その奥の中殿筋、小殿筋
②大腿四頭筋のうちの外側広筋
これらの筋肉のハリやコリを丁寧に取ることでほとんど解消されます。
首などと異なり構造というか筋肉の走行が単純なので一つずつ取っていけば特に問題ありませんが、難点は筋肉のハリやコリが強い場合、施術がかなり痛いという事です。外側広筋などは手のひらで軽く圧をかけて摩る程度でもすごく痛いことがあるので患者様の具合をよく見ながら進めていきます。
臀部の深い部分は鍼が必須です。これもかなり強く響くことがありますし、治療開始して間もない頃は大きなLTRが出ます。
*LTRとはLocal Twich Response(ローカル・トゥイッチ・レスポンス)の略で日本語では部分筋攣縮などと言われます。これは鍼がコリに触れると”ビクン”と一瞬、筋肉が勝手に収縮する現象です。コリの中でも特に悪いコリで生じることが多いです。治療が進むとだんだんでなくなってきます。
ただ、施術をやっているときは痛くても終わった後、一気にすっきり軽くなるので施術する価値は十分あります。
*腰痛の酷い方や、スポーツ選手の場合は上記に加えてハムストリングスの硬結・短縮が見られることが多いので解消するための施術を行います。

下腿部でだるさを感じる場合、
まず
①ふくらはぎの筋肉のコリを丁寧に取っていきます。
ふくらはぎは3層の筋肉が積み重なっていますのでそれぞれの層ごとに硬い部位を見つけて施術します。足をつる時と異なり、だるさの場合は第3層の後脛骨筋のコリが奥からうずくような痛みを発していることも多いので入念に施術していきます。この後脛骨筋は、たいてい左右どちらかが明らかに他方より硬くなっていることが多いのが特徴です。
②前脛骨筋と腓骨筋: よく走る方や早歩きの方は前脛骨筋が非常に硬くなっていることが多いです。この筋肉は絶えず遠心性収縮をさせられるので疲れがたまりやすい部位です。腓骨筋は見落とされがちですが、特に球技をやる方は疲労がたまりやすくとても硬くなっていることが多い部位です。
③足底: 足底の筋肉で見落とされがちなのは内側(内くるぶしから拇趾にかけて)にできているコリの存在です。たいていの場合、左右どちらか一方にのみ存在します。場合によっては小さく細いコリですが下肢全体の疲労感と関係するくらい大きな影響を及ぼしていることがあります。


股関節痛・膝関節痛
下肢に限ったことではありませんが、関節痛(特に変形性関節症などによる痛み)について言えることは、事故やけがによる場合を除き、いきなりなるわけではなく長年にわたる関節周囲の軟部組織(筋肉・筋膜・靭帯・関節包など)の血行不良ないし疲労が蓄積して関節軟骨に過剰なストレス(衝撃・摩擦)、関節軟骨の酸欠による結果であるという事です。
”老化”の一言で済ませてしまえばそれまでですが関節周囲の軟部組織(筋肉)を良い状態に保っておけば関節にかかる負担はかなり減らせるので(症状が出る前が理想ですが)出始めたら早めに対処する方が良いです。変形性関節症は、特徴の一つとして、動き始めに痛みが出て動いているうちに痛みがなくなる(動作開始時痛)というのがあります。これが結構厄介で、「動けば大丈夫だ」、ということで治療の開始が遅れて関節の変形が進む落とし穴となりえます。
人が歩いたり走ったりするとき、瞬間的に体重の何倍もの衝撃が各関節にかかります。関節周囲の筋肉がしっかりしていればその衝撃をかなり吸収することができるのですが、筋力不足や筋肉量はあってもハリやコリのため力がちゃんと発揮できない場合、衝撃がまともに軟骨部分にかかるのでその蓄積で傷みが早くなります。それに加えて、血行不良で関節内が酸欠や栄養不足に陥ればなおさら修復不全で痛みが早くなります。
骨そのものは自分で位置を決められるわけではなくて周囲の軟部組織の張力の総合によって位置が決まるものです。ですので単に反対方向に引っ張ったりひねって元に戻るというものではなく、筋肉・筋膜などのコリ・短縮による引っ張りを丁寧に解消することが根本的な解決法です。
*勢いをつけて引っ張ったり捻ったりすることは意味が無いどころかそれ自体が新たな痛みや損傷の原因となりうるのでお勧めしません。
また、変形性関節症、例えば膝の変形性関節症で膝の内側が痛いといった場合、軟骨や骨そのものから痛みが出ているというよりは細かく見てみると、関節部分を覆っている靭帯や関節包などの膜組織が痛いということが大変多いのでその場合、痛みを取ることは十分可能です。
周囲の靭帯の痛みを取ることは可能とはいえ、変形してしまった骨や関節軟骨そのものは、基本的に戻らない(近年、一定の条件のもと戻ることが発見・報告されていますが簡単ではありません)のでそうなる前に元の原因である周囲の筋肉などのコリやハリを早めに解消しておくことが大切です。

足をつる
ほとんど同義語として”こむら返り”とも言われますが、非常にありふれた症状です。
原因については水分不足、ミネラルバランスの乱れ、疲労、脊柱管狭窄症、糖尿病…など様々なものが候補となりえます。
当院では足をつることを主訴として来院される方は少なく、他の症状の治療のついでに治療を行うことが多いです。脊柱管狭窄症などの神経的な要因がある場合は事情が異なりますが、当院で診る限りほとんどの場合は原因はふくらはぎの筋肉の血行不良と(最大公約数的に)見受けられます。
つまり、血行不良を引き起こすような要因、歩きすぎ(筋疲労)、立ちっぱなし(筋疲労)、冷えなどで筋肉細胞のエネルギー不足や代謝異常が起こり → 運動神経の異常興奮といったメカニズムが考えられます。
第一層の腓腹筋の内側、第二層のヒラメ筋のコリを丁寧に取れば比較的容易に改善されます。
治療の難点としては、鍼だとかなり響きがきつい(加えて鍼が当たった時、驚くほど大きな筋攣縮(LTR)が出ます)ことが多いので丁寧にマッサージを行った後、必要であれば鍼を用いる治療を行います。
足をつる、という時は”だるさ”の時と異なり第三層の後脛骨筋の関与は薄いと思われます。
(図:『Netter 解剖学アトラス』, F.H.Netter, 訳 相磯貞和, 南江堂.より)