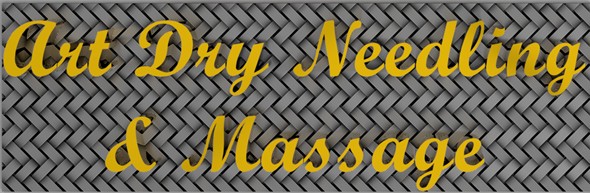当院のやろうとしていることはいたってシンプルです。
―核となっているのは2つの論文―
鍼灸マッサージ業界に入って驚くのは数えきれないほどの治療法、流派が存在することです。
東洋医学、中医学(漢方)のように、昔から続くとされるものもあれば、トリガーポイント療法のように近年、世界規模で認知されるようになったもの、整体のように良く分からないままいつの間にか市民権を得てしまっているもの、骨盤の歪み矯正だとか筋膜リリースや肩甲骨はがしのようなNew Comerも続々と追加されて増える一方です。これらの中でさらに細分化されて枚挙にいとまがありません。
国家資格は取得したものの果たしてどんな風にやっていくべきか?というのは施術者ならみな悩むものです。私もあれこれ見ようと努力した時期もありますが、”長く続いている”とか、”多くの人が信じている”ということと中身の正しさは全く関係ない訳で、どれも“信仰心”をもって臨まないといけないので、私のように理屈っぽい人間には選びようがありません。
冷静に考えてこれだけ多くの治療法が世の中に存在し、いずれも他を凌駕することなくそれなりに存続できている、ということは要するに、どれも同じ程度に効果があり、またどれも同じ程度に効果がない、つまり、ドングリの背比べ状態だということを意味します。
もし圧倒的に効果に勝る治療法があれば、ある程度の期間が経過していけば選択圧がかかり収斂していくはずです。その選択圧を逃れてむしろ発散傾向さえ見られるということは、大して効果に違いがない中で患者さんはあちこち巡らされているということです。
もちろんそこまで重症でなかったり、若かったり、効きやすい体質の方も多いので、常識的な治療であればそういった患者様の役に立っているのは紛れもない事実です。
それはそれで大変尊い事なので良いのですが、それでもどうせ自分の一生の仕事とするならば、他人の作ったファンタジーの中で踊らされるのではなく、自分が心底納得できて、尚且つ治らないで困っている少数者に役立つような施術は無いものか…と論文をあれこれ読んでようやく見つけたのが
1979年にチェコの学者KAREL LEWITによって書かれた論文「THE NEEDLE EFFECT IN THE RELIEF OF MYOFASCIAL PAIN」です。

そしてその後、
1990年に川喜田健司によって書かれた「針灸刺激の抹消受容機序におけるポリモーダル受容器の役割」
という論文に出会うことができ縦糸と横糸がしっかり結ばれたような状態になって私の施術の方向性が決まりました。
物理学や数学で3体問題とか2重振り子なども話がありますが、たった2つ、3つの因子が絡むだけでこれだけ難解になってしまうのに、人体の複雑さはレベルが違います。一体いくつの因子が絡んでいるのかさえ分からない。
施術の流派ごとにたくさん「理論」がありますが、常識的に考えて人体の全体像も解明されていないのに「〇〇理論」だなんておこがましい。そんなもの打ち立てられるはずがない訳です。
山中Dr.がIPS細胞の作製技術の確立の件でノーベル賞を受賞してからもう随分と時間がたちますが、いまだ臨床現場で広く使われるには至っていません。世界中で必死に実用化の先陣を切るべく寝る間も惜しんで頑張っているにもかかわらずです。つまり、仮に一つの仕組みが分かったとしても人体の複雑さははるか上をいっているわけです。
分かったような振りして腰痛の時はああしろ、こうしろと平気で講釈垂れる施術家のような厚かましさを貫く精神的スタミナのない私としては、自分が確実に手に負える範囲だけ明確に理解して正確に実行できればそれで十分です。
1つ目の論文は実践面での支柱となるもので、要するに「当たれば効く」ということを実験的に明らかにしたものです。
経験的に鍼やマッサージがある条件下でとても効くことはわかっていたので、その条件が知りたかった。→ The effectiveness of treatment was related to … the precision with which the site of maximal tenderness was located by the needle.(*1) ああ、当たれば効くのね!と、その確証が得られれば私にとってそれで十分です。
じゃあ誰よりも正確に当てられるようになろう、と狂ったように毎日何時間も色々な練習を繰り返しました。素人の方からすると何を当たり前のこと言ってんだと思われるかもしれませんが、全然当たり前ではないんですよ。プロ野球でも同じ道具を使ってプレーしているのに毎年3割超える選手もいれば生涯1回も達しない人もいます。鍼灸治療院はたくさんありますが、女性の首・肩こりや頭のコリ(緊張型頭痛)などで頻繁に遭遇する、そうめんみたいな幅の細いコリを正確に狙って治療していける鍼灸院は相当少ないと思います。
(*1) KAREL LEWIT, THE NEEDLE EFFECT IN THE RELIEF OF MYOFASCIAL PAIN, Pain, 6 (1979) 83–90.
そして当たって効くのは良いとして、その時何が起こっているのか?
それを説明するのが2つ目の論文です。
この論文は別にこれは「理論」なんて大それたものではなくて、ポリモーダル受容器(polymodal receptors)という痛み刺激を感知するセンサーの振る舞いを説明したものです。「理論」ではなくて、生理学的な「事実」で、どんな生理学の教科書にも載っているものを鍼刺激の観点から少し詳しく説明しただけです。(鍼灸刺激の抹消受容機序におけるポリモーダル受容器の役割:川喜田健司)
ある刺激が入ったときにポリモーダル受容器がこのよう振舞いますよ、ということは「事実」ですからひっくり返しようがない。
個人的な意見としては「理論」に基づく治療は弱いです。人体のすべてが解明されてるわけではないのでどうしても説明しきれない穴ができますから必ず例外や筋が通らないことが出てきてしまいそれを説明しようとして話がどんどん複雑になっていきます。
逆に、「事実」に基づく治療は安定感が違います。なんせ「事実」は「事実」ですから同一条件下では再現性があります。
これで悪い部位(コリ)がなぜ痛みを生じ、鍼が当たればなぜ響きが生じ、その後筋肉痛などを経てコリや痛みが取れるのか、ということが説明できるようになりました。
あとはひたすら、更に精度を上げていく努力と響きの大きさをコントロールできるよう努力を続けていくのみです。
以上が当院のスタンスです。