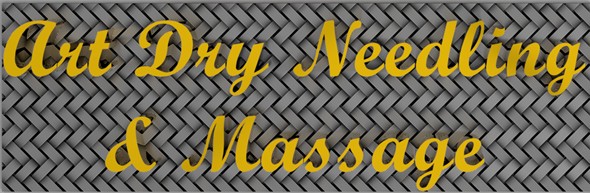局所から全体へ良い箇所を広げていきます
明言されていることは少ないかもしれませんが、鍼灸マッサージの治療は、鎮痛効果を目的とするものと、コリそのものを取る(それにより痛みをなくす)ことを目的とするものに大きく分かれます。
前者の、鎮痛効果を目的とする治療は、「症状の軽度の方」や、およそ半数いるとされる「体質的にとても効きやすい方」にはそれで十分なのですが、往々にして一時的効果に過ぎないことがあること、そして根本的な難点として鎮痛効果の出にくい体質(およそ3割)の人には一時的な効果さえ起らないという問題点があります。(☞ 浅い鍼(軽い刺激)の治療の効果とその限界)
仮に痛みは抑えられたとしてもコリがあるのを放っておくのが感覚的に嫌だという私の個人的な価値観と、日本において前者を目的とした治療院が主流なので当院ではそこで解決を見ない患者様の受け皿になることをコンセプトとして開設していることもあり、当院では後者に絞って施術を行っています。
筋・筋膜性疼痛(MPS)は、基本的には「血行不良」が原因でコリができそれが痛みを生じている状態ですが、そのような場所(コリ)のポリモーダル受容器は過敏になっていますので、鍼、マッサージのどちらかを用いて適刺激を入れて不活性化させていくことで血流を改善し、「コリ」を解消し、それに起因する痛み(慢性痛)を軽減・除去するしていきます。
過敏になったポリモーダル受容器が刺激を受け、神経性炎症の過程を経て不活性化されると、治療前と比べて圧痛、自発痛・運動痛は明らかに軽減しますし、何よりもご自身で触られるとコリ・筋硬結の硬さ・大きさが以前とまるで異なることがお分かりになると思います(氷が解けて小さくなっていく感じです)。特に首や肩はすぐ手が届く場所なので変化に驚かれる患者様が多くいらっしゃいます。

そして治療の進め方ですが、
東洋医学などで議論される治療の際の考え方として「本治(原因療法)」「標治(対症療法)」というものがあります。簡単に言うと、本治とは体質改善を目的とした根本治療、標治とは今ある症状に対応する対症療法ということです。何となく察しが付くと思いますが、東洋医学においては本治が優れた治療とされ、標治(対症療法)は低く見られる治療法です。日本においては鍼を用いた治療といえば圧倒的に東洋医学が主流なので対症療法というのは劣る治療法という評価が一般的ということになります。
一方、当院では基本的に反応の強い悪い部位からどんどん不活性化させていけば良いと考えて治療を行っています。例えば、肩こりであれば、まず痛みを発している肩の筋硬結を一番初めに取ってしまいます。おそらくこういったやり方は標治と評価されるのでしょうが、
もともと東洋医学はコリやそれに起因する痛み(筋筋膜性疼痛:MPS)を治療することが目的ではなく、五臓六腑の乱れを治すことが目的です。
当院としましては、「肩が凝って痛い」と訴えている患者様の肩の筋肉が実際に硬くなっていて、その部位のコリを正確に捉えれば確実に柔らかくできて痛みが楽なることが分かっているなら、まずそこを治療するべきで、わざわざ「証」を立てて違う場所に鍼を打つ必要はないだろう、という考え方です。
もっとも、近年注目が集まっている筋膜などの結合組織のつながり、あるいは細胞や離れた臓器の作る複雑なネットワークの議論からも分かるように、身体は全体につながっています。また、TP(トリガーポイント)療法の考え方のように、痛い場所と悪い部位が必ずしも一致しない(関連痛)ことはよく知られていることですし、臨床の現場でも実際にそういった場面には頻繁に遭遇することです。
したがって、結局のところどんな症状でも最終的には範囲を広げてみる必要はある(例:腰痛などを本気で治そうと思ったらたいていの場合、下肢・臀部をしっかり治療しないといけない。)のですが、基本的な方向としては一番気になるところから関連する箇所へ、患者様のご希望(どこまで求めるか)と条件(お時間・ご予算)に応じて治療を進めていきます。