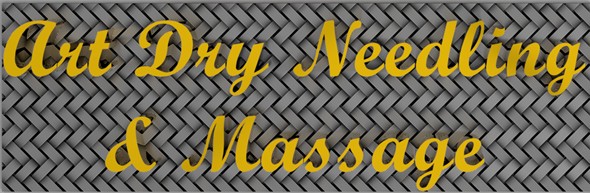血行不良はなぜ悪いのか?
血行不良は、単なる肩こり、首こり、腰痛…などの運動器の疾患・トラブルに限らず内臓疾患も含めた万病の元であるということは、どのような身体観や医学的観点(西洋医学・東洋医学)に立っていようと常識的なコンセンサスになっています。
ご周知のとおり、鍼灸やマッサージ治療も「血流の改善」を主たる目的として行われています。
当院も”血行不良”→”コリ”→”痛み”という基本的理解を前提に”血流改善”→”コリの解消”→”痛みの除去”を目的として日々治療を行っています。
ここでは通常よく聞くような話とは少し違う角度から掘り下げて考えてみたいと思います。どうでもよい人にはどうでもよいかもしれませんが興味深いと思ってくださる方には面白い話になると思います。
要約 :血流が大事(=血行不良が悪い)なのは以下のことに直にかかわるから
・「生きていること」を”物の例え”で「命を燃やす」と言いますが、実は”物のたとえ”(比喩)ではなくて”本当に”燃やしています。「人間が生きている」のは「ろうそくが燃えている」のと基本的に同じことです。
・人間の身体の中の分子は、見た目では全く変化がなくても、あらゆる部位で常に激しく入れ替わり続けている。=動的平衡
・人間の身体も含めた、この世のあらゆる形ある物は、必ず壊れる(無秩序化)方向に進んでいく。=エントロピー増大の法則
生きているということを、別の表現で表すならば、エントロピー増大の法則に逆らい続けているということ。
壊れるより前に自ら壊して作り変えることで死(無秩序化)を遅らせている。
そのための物質のやり取りは血液によって行われる。
生物のエネルギー源:ATP
人間が生きるためには食事からエネルギーを摂取する必要があります。
しかし、多くの人に誤解されているように食事のカロリーが直接、人間(生物)の活動エネルギーとして使われるわけではありません。摂取した栄養を、酸素で燃やしてATP(アデノシン三リン酸)に変換し、それを分解するときに放出されるエネルギーで生命活動を行っています。ATPは、脳であれ、筋肉であれ、内臓、皮膚、…すべての細胞の働くエネルギー源となる物質なのでお金に例えられ「生命のエネルギー通貨」と呼ばれます。
ろうそくも人の命も本当に燃えています。
ろうそくはパラフィンであろうと、脂肪酸のグリセリドであろうと、要するに炭素と水素の化合物でそれを空気中の酸素で燃やし(酸化)、熱や光エネルギーが生まれます。燃えるとCO2が出ます。
人間が、エネルギー源として摂取する炭水化物も、読んで字のごとく、要するに炭素と水素の化合物でそれを呼吸で取り入れた酸素で燃やし(酸化)、熱やATPを生み出し、それが体温や細胞の活動エネルギーになります。吐く息としてCO2が出ます。酸化のスピードが緩やかなので炎が出たり煙が出たりしませんが基本的に同じことです。
(正確には肺での呼吸ではなく細胞内呼吸といって細胞内のミトコンドリアが栄養と酸素からATPを作り出しています。)
血流との関係
ATPという生命のエネルギー通貨を作るためには、栄養と酸素が必要です。これらは血液によって運ばれます。血行不良は結局、栄養不良、酸欠、ATP生産不可、→細胞の活動エネルギーが枯渇という事態を招きます。
見た目は変わらないのに人体は常に中身が入れ替わり続けている。
「サプリメントは効果的?」で分子生物学者の福岡伸一氏の動的平衡(元はシェーンハイマーの動的状態)という考え方をご紹介いたしましたが、ここでもこの概念がスタートになります。
簡単に表現すると
身体のあらゆる部位は中身が常に激しく入れ替わっている
つまり、一見変化が無いようであっても脳細胞、筋肉、脂肪、血管、骨…あらゆる部位は常に、壊しては、食べて取り込んだ材料で再構築する、ということを繰り返している。
その際、元の食物が有している情報を完全に消し去るために分子レベルにまで細かく分解する必要がある、という事でした。
これが消化という作業であり、元の情報を完全に消えているから牛を食べても牛になることはありません。
外からは全く分かりませんが、我々の身体は、数カ月程度で中身が全部入れ替わってしまうくらいのスピードで変化し続けており、その実態を正確にとらえるならば身体はもはや容れ物でさえなく、通りすぎつつある分子がほんの一時的に形を作っているだけの存在ということになります。
このような状態を動的平衡と呼びます。
血流との関係
①この、壊す場面、再構築する場面の両方において当然エネルギーが必要ですが、もちろんこれもATPを分解して得られるエネルギーで行われます。
②また、この場面では炭素(C)を燃やす、というのではなく、体の構成要素であるアミノ酸(たんぱく質)、つまり窒素原子(N)などが速やかに運ばれてこないといけません。
この2つのいずれも血流によって成されますから、血行不良状態では、本来予定されている人体の建築(再建築)が設計図通り行われなくなってしまいます。
なぜこんな無駄なことを . . .?
→ 生きるとは、エントロピー増大の法則に抗い続けるということ。
動的平衡の事を知り、誰でもまず思うのが「なんでわざわざそんな無駄なことをやってるのか?」ということです。
損傷している部位を新しい分子(物質)で入れ替えるなら分かりますが、まったく正常な部位もわざわざ自ら壊して物質の入れ替えを行っています。はた目には穴を掘っては埋めて、、、を繰り返しているようにも見えます。
例えば、個体発生後はほとんど分裂も増殖もしないことで有名な脳細胞でさえ、そのDNAを構成する原子・分子は常に分解され新しい分子・原子に置き換えられています。増殖・分裂する予定がないのですから自己複製されることはありません。本来、(よほどの損傷などが無いなら、あるいは損傷があったとしても)わざわざコストをかけてメンテナンスする必要は無いはずです。
なぜこのような、一見無駄にしか思えない労の多い方式を取っているのでしょうか?このことを考えると血行不良が悪い本当の意味が見えてきます。ここでも福岡伸一氏の一連の書籍を参考に考えていきます。
エントロピー(entropy)という概念があります。
もともとは1865年にルドルフ・クラウジウスによって提唱され、熱力学におけるエネルギーの不可逆的な変化を説明するために用いられましたが、統計力学や情報理論などでも用いられるようになり、現在では(半ば日常用語的にもなりつつある?)もっと広く使われるようになってきています。
簡単に言うと、無秩序やランダム性、不確実性に関連する科学的な概念で、もっと簡単に言うと「乱雑さ」「無秩序さ」の程度を表すと理解できます。
そして、この宇宙のおよそすべての事柄は(時間が逆転すると考えないなら)このエントロピー(乱雑さ・無秩序)が増大する方向に不可逆的に進んでいます。これをエントロピー増大の法則といいますが、
身近な例で言えば、お風呂のお湯や暖かい飲み物は必ず冷める、茶碗やコップに限らず石や岩のような頑丈な物も含めておよそ形あるものはいつか壊れて細かくなっていきますが(散らばっていく=乱雑さが増す)、その逆はありません。
つまり、長い年月はかかるかもしれませんがやがては岩や石は砂粒になっていきますが、砂粒が自然に石や岩になっていく(=乱雑さが減り秩序化していく)ことはありませんし、コップが割れることはあってもガラスの破片がコップになることはありません。
このように常にエントロピーは増大する方向に進みます。
生物でエントロピーが増大(最大化)するということは個体の死を意味します。(身体を構成していた物質はバラバラになり無秩序化して土に帰っていく。)
このエントロピー増大の法則にできるだけ逆らおうとする努力が、生きているという事になります。ばらばらの無秩序にならないで、人体という秩序ある状態で居続けたい。
エントロピー増大の法則に抗うための手段
とても長いスパンで見たら無駄な努力と言えば無駄ですが、それでもエントロピー増大の法則に少しでも抗う一つのやり方として、
道路や建造物のように、石や鉄筋コンクリートなど硬い素材を用いるなど出来るだけ頑丈に作ることで出来るだけ長く壊れないようにして、エントロピー増大の法則に抗う方法もあります。
ところが生物はこのような方法を取りませんでした。
取ったのは柔らかく緩い設計という戦略です。
エントロピー増大の法則に先回りをして、予め自分から自分自身を壊して再構築するという方法です。決定的に無秩序化する前にあらかじめ新しいものに取り換えてしまうことで無秩序が自分の中に溜まりにくくしているのです。
生物が正常に生きるためにはとにかく「秩序」が大事です。手、足、口、内臓、各パーツがあるべき場所にあるべき大きさ、形で存在するという解剖学的な意味においても、気温・環境の変化があっても体温や血糖値が一定に保たれていること(ホメオスタシス維持*1)という意味においても体内の秩序を保つということが特に動物の場合は重要です。
体内の無秩序の一番の例が悪性腫瘍・ガンです。周りとのバランスを無視してひたすら自己増殖し続けます。
――(余談ですが)ところが、植物においては少し事情が異なり、このような内に向かう秩序の厳密さは動物よりも少ないと言えます。植物の場合、基本的に悪性腫瘍・ガンは存在しません。研究者によっては植物にもガンはある(細菌感染によりこぶが出来る)と説明していますが動物におけるガンとかなり異なり浸潤したり全身に転移するなどというものではありません。昆虫などを含めた動物の場合は、手足の数や配置される場所が正確に定まっているのに対し、植物の場合は基本的に必要な場所にどんどん増えていけばよい、つまりそれが枝、であり、葉っぱなので動物よりもエントロピーが大きい存在だと言えるかもしれません。 ――
それでも追いつかずに少しずつ溜まった無秩序がやがて個体を死に追いやります。(エントロピーの最大化)
血流との関係
生きている=身体は常に激しい分子の入れ替え行うことでエントロピー増大の法則に抗っていますが、このシステムを何によって具現化しているのかというと血液によってです。
老廃物(これは自己の体内に溜まりつつあるエントロピーです)を外に捨てるのも、栄養(「糖分などのエネルギー源」や「アミノ酸などの細胞の構成要素」など。これは自己の体内に取り込むべきエントロピーです)を運ぶのも血液を通して実現されています。
身体には数十兆の細胞があると言われますが、基本的に一つ一つの細胞は毛細血管と接して酸素や栄養を受け取っています。筋肉も、例えば、前脛骨筋など一つの筋肉には数千本の筋線維(筋肉細胞)がありますが、その一本一本に毛細血管が張り巡らされています。
肩こりや腰痛など筋肉にコリがあり、筋肉やその周囲に血行不良があればその部位では確実にエントロピーが増大することになります。
血液を介して身体を構成する分子・原子を絶えず入れ替えてなければ、絶えず晒されているエントロピー増大の法則による圧力から逃れることはできないのに、血行不良で栄養・物質のやり取りが出来なければ同じ程度の悪さの状態でさえいられないからです。
物質レベルでも質の劣化(筋膜組織・筋線維の硬化、短縮)を起こし、働きの面でも機能異常(痛みやしびれ)を引き起こすことになりますが、血液の流れがなければ治癒の生じようがないので、状態が酷くなる(=エントロピーの増大)ことはあっても、エントロピー増大の法則の不可逆性によりその逆にはなりえません。
ドライニードリング(鍼)やマッサージとの関係
ドライニードリング(鍼)やマッサージによって、血流を改善し肩こり・腰痛などを解消するということはエントロピーを減少させる行為と表現することが出来ます。
一度変形した関節や骨は元に戻ることは難しいです。骨に限らず身体の多くの器官に生じる老化などによるは不可逆ですが、筋肉(の凝り)は元に戻ることのできる数少ない器官と言えます。
数十年来のコリが治療で解消されて、血液をたくさん含んだフワフワした感触になるということはある意味、時間を巻き戻しているとも言えます。
注)
*1)ホメオスタシス(恒常性):19世紀のフランスの生理学者クロード・ベルナールは生命現象を「結局は、内部環境の恒常性を持つという事が唯一の目的」といい、この考えを実験的に示し「ホメオスタシス」と名付けたのが米国の生理学者ウォルター・キャノンです。本コンテンツとの関係で言えば、エントロピー増大の法則に逆らい続けること=ホメオスタシス維持という事になります。
エントロピー増大の法則により、ただでさえ生物は、常にホメオスタシスが維持されにくくなる方向に進んでいます。血行不良はそれを加速化させることになります。
鍼灸マッサージ治療は血流改善によりホメオスタシスを維持し、エントロピーの減少に導く行為ということができます。