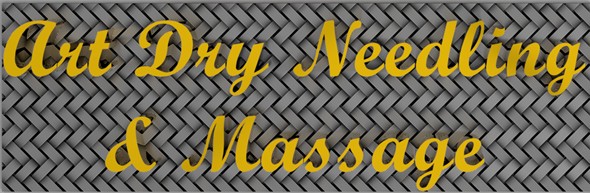施術時に鍼の響きはあった方が良いのでしょうか?
鍼やマッサージ治療に特有のズーンといういわゆる「響き」の感覚がありますが、治療効果との関連で、あった方が良いのか、なくて良いのか(あってもなくても変わらないのか)という事が日本ではよく話題になります。
*個人的な印象ですが、海外の文献では、響き(heaviness, soreness, numbness….)やLTR(ローカル・トゥイッチ・レスポンス:部分筋攣縮)は鍼の効果を確実にする現象、当たり前のことを聞くな、という感じで響きの(メカニズムについての議論はあっても)要否については議論にすらなっていないように見受けられます。
当院の立場
マッサージや鍼の施術中に悪い部位に当たっている時の感覚である「響き」は、俗に「いた気持ちいい」と表現されたりもしますが、これは西洋医学的には、侵害刺激を感知し痛みを伝えるポリモーダル受容器・C線維(Aδ繊維)の反応によると考えられます。
ポリモーダル受容器の受容器としての性質(コリの程度の悪い部位では敏感になり反応しやすくなるという性質)からすると、悪い部位に正確に刺激が入った場合、響きが生じることは避けられないということになります。したがって、この意味(悪い部位に当たったことの保証としての意味)で響きはあった方が良いと言えます。
しかし、それほどコリの程度が悪くない場合、細い鍼では当たったとしてもポリモーダル受容器が反応しないことが考えられます。この場合(当たってはいるがそもそも反応が出るレベルの悪さではない場合)は響きがなかったとしても施術が悪いとは言えない(仕方ない)ことになります。もしこの部位で響きを出すなら太目の鍼を使用して侵害刺激の程度を上げることが考えられます。
図(1) 侵害受容器①②と非侵害受容器③の活動 (熊澤孝朗, 1984)

以上は、ポリモーダル受容器の受容器としての性質から考えた話です。(=悪い部位では敏感になっているので当たれば響きが出る。つまり、響きは悪いところに当たったことの保証の意味を持つ。)
では、今度はポリモーダル受容器の効果器としての性質から見た場合はどうでしょうか?
下図(2)で示されているようにポリモーダル受容器の効果器としての様々な性質(血管拡張作用・免疫に対する作用、自律神経系に対する作用、鎮痛作用…等。)を考えると響きはあった方が良いというのが自然な結論になります。
鍼や指が当たってポリモーダル受容器が刺激される(=響き)と、これだけの様々な効果が期待できるからです。
もちろん鍼やマッサージによって「侵害刺激」、あるいは侵害刺激に至らない程度の「機械刺激」が外部から生体に与えられている訳ですから、響きがなくても何らかの生理的反応は当然でます。この生理的反応も立派な治療効果だと考える立場なら響きは無くて良いという事になります。優しい刺激で長期間かけて体質改善を目指すというような治療スタイルも実際に日本では好まれています。
しかし、
効果がある無し(効果の有無)という話と、どのくらいの効果があるか(効果の程度)という話はまったく別です。効果の程度を問題にする立場からはポリモーダル受容器がしっかり反応する程度の質と量の刺激(=響き)で治療を行うべきだと考えるのが自然です。
当院は思いっきり後者の方なので一回一回の治療に、わざわざ時間とお金を使って受けた甲斐があった、と思えるはっきりした効果を出すために響きは当然あった方が良いと考えています。
(実際にはもう一つ、難しい問題として「効果の有無」「効果の程度」の話とは別に、響きが「好き・嫌い」という「感情」の問題もあります。必要性・有用性は理解できるが感情的に好きではない・苦手だという場合です。どうしても不可という方は仕方ありませんが、ぎりぎり受容できるかなという方であれば、響きの強さを出来るだけ最小・最適量になるようにコントロールしながら効果をあげていくことを目指していきます。)
詳しくは ポリモーダル受容器や鍼の痛みについて等のコンテンツをご参照ください。
☞ 浅い鍼の治療
(ポリモーダル受容器が適刺激を受けた場合に生じる反応)

(出典:Kumazawa T : Function of the nociceptive neurons. Japanese Journal of Physiology 40: 1-14,1990 より)