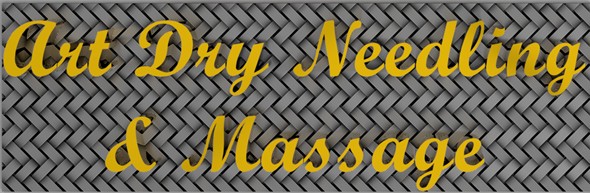鍼治療に対する期待が鍼の効果に与える影響 – ランダム化トライアル
ここでは、864人を対象にして行われたランダム化トライアルの結果をご紹介いたします。
ランダム化比較試験とは?
*ランダム化比較試験 (randomized controlled trial : RCT、または無作為化比較試験)とは、直接的な実験的コントロール下にない要因をコントロールするために用いられる科学的実験の一形態のことです。例として、薬物、手術法、 医療機器 、食事療法などの医療処置の効果を調べる臨床試験があります。
新薬を試す場合で言えば、比較したい群(新薬群 ⇔ プラセボ群)に入るサンプルが、ランダムに決められて薬効を調べる実験が行われます。
→ 薬に効果があるかないかは「薬を飲んだ集団」⇔「飲まない集団」を比較することで知ることが出来ますが、被験者は様々な属性(性別、年齢、体質…など)を持っているのでこれらの背景因子が揃っていないと、薬が効いたのかそれ以外の原因のせいでこの結果が出たのかが分からなくなります。
したがって、明らかにしたいこと(=薬を飲んだ飲まないの差)以外の因子を集団間でそろえるためにランダム化という手段がとられます。ランダム化を行なったランダム化比較試験は、得られる結果のエビデンスがとても高いことで知られています。
概要
鍼治療に対する正の「期待」は受ける治療が本物鍼か偽鍼かに関わらず良い結果を予見することが示された。
幾つかの慢性痛に対する鍼治療に関するRCT(ランダム化比較試験)を再分析した結果、症状改善への「期待」が唯一の正確に結果を予見できる要因であった。
実験内容
864人の患者(片頭痛:302人、緊張型頭痛:270人、慢性腰痛:298人、変形性膝関節症:296人の患者)を対象に、1回30分の治療を計12回行い、どのようなファクターが臨床効果に影響を与えるかを調べました。
実験は、以下の3グループに分けて行いました。
・通常の鍼治療のグループと
・シャム鍼として最小刺激の鍼刺激(ツボでない場所に浅く刺鍼)のグループ
・鍼治療を行わないグループ(コントロール群)
被験者に行われた質問事項
1・一般的に鍼はどれくらい効果があると思っていますか?
とても効果的・効果的・わずかに効果的・効果的でない・分からない
2・あなたは自分が受ける鍼治療に、個人的に何を期待しますか?
完治・明らかな改善・わずかな改善・改善ナシ・分からない
3・(3回の治療後)この治療があなたの症状を改善できるとどのくらい確信していますか?
→ 症状に50%以上の改善が見られた被験者を反応者(responder)として分類した。
様々な条件(性別や年齢、慢性痛の期間など)を考慮し分析した結果、治療結果に対する「期待」(expectations)が一貫して大きな改善への最大の要因であることが示された。

改善が見られた Responder の割合は、治療効果への高い期待と確信を抱いているほど高い
→ 治療の効果に対する期待と確信が明らかに実際の効果に影響していることが明らかになった
その他
他にも解析の結果、
・慢性腰痛、片頭痛、緊張型頭痛患者においては本物鍼と最小刺激鍼の間で有意な違いが確認されなかった。
・変形性膝関節症患者においては、本物鍼は最小刺激鍼よりも統計上、有意に結果に違いが出た。
・変形性膝関節症患者への本物鍼は、最小刺激鍼よりも追加的な特定効果が見られたが、その効果量はわずかで持続期間も限られていた。
・最小刺激鍼の効果は明らかに非治療群よりも大きい。
この論文を読んで . . .
A: 患者様が持つ鍼への期待感こそが症状改善に深く関連している。
B: 鍼治療は何もしないよりは明らかに良いが、「ツボに打つ正式な鍼治療」と「ツボを外して浅く打つ鍼」で基本的に効果は変わらない。
ということが示され
治療を受ける患者様にとっても、鍼灸マッサージ師にとっても一見、ショッキングな結果となっていますので一考してみたいと思います。
まず、864人という十分な規模で、ランダム化比較試験(通常の実験・調査よりも質が高いとされる)を行って出た結果ですので、「たまたまこうなった」という言い方で片づけるべきものではありません。
A:について
鍼灸マッサージに限らず投薬や手術を含め、どんな治療でも、「治療効果」は「プラセボ効果」+「その治療特有の効果」の合計で成り立っているので、鍼治療の効果に「プラセボ効果」が関わること自体はまったく当然のことです。「期待を大きく抱く方が効果が大きい」という当たり前の結果が示されたという事です。
B:について
問題は「ツボに打つ意味」がどのくらいあるのか?という点です。これがあまりにもわずかなものでしたら時間とお金の無駄になってしまいます。
まず、「鍼の効果」について考える場合、当院が常に問題だと考えている点は「効果」の意味です。
「(一時的な)鎮痛効果」をいうのか、「痛みを出す根源(いわゆるトリガーポイント)を除去することで生じる鎮痛」の意味での「効果」をいうのか、この2つは一般的に分けて語られることはありませんが、メカニズムがまるで異なるので、本来「効果」の一言で同じに扱われるべきものではありません。鍼の事を調べた論文を読む場合、常にここが問題となっていると当院では考えています。(多くの論文はある症状に効くとされている「ツボに打つ」ことで症状の改善(多くは「痛み」が減った)が見られたかどうかを調べています。)
(一時的な)鎮痛ということなら、最小刺激鍼(浅い鍼)で効果が出る人が多くいることは他の様々な研究でも示されていますし、特に日本においてはその種の治療院が多いので多くの患者様がその恩恵を受けているという事実からも実証されています。
次に、はたして「ツボ」にどこまで意味があるのか?ということについてですが、この研究では浅い鍼を「ツボを外して」打っている群と、「ツボ」に打っている群で効果に差がないことが示されています。
実はこの事を指摘する論文は結構あって、鍼灸治療に対する科学的思考の先駆者-Felix Mannのコンテンツでもご紹介した通り、Mannの調査でも、fMRIを用いた鍼刺激についての脳反応の調査でも鍼を打つ場所がツボか、ツボでないかは鎮痛効果を得る上で重要な要素ではありませんし、ツボ特有の脳反応というものも確認されていません。
当院ではツボと経絡に他の部位とは異なる何か特別な効力があると考えておりませんので、この論文の結果は意外性はないものです。(ただし、この立場は日本においてはかなり異端であるという事をお断りしておきます。)☞東洋医学について
しかし、ツボに特別な効果があるという前提に立つ場合、到底素直に認められる結果ではないので何か否定する理由をつけなければなりませんが苦労することになります。この辺りの苦悩は鍼の効果を調べることの困難さのコンテンツや添付論文などをご参照ください。
「効果」に対するもう一つの見方
鍼の「効果」を「痛みを出す根源(コリやトリガーポイント)を除去することで生じる鎮痛」の意味で用いるならば話は大きく変わります。
この場合、痛みの根源の除去による痛みの除去なので基本的に心理的効果(関係ないことはないでしょうが)に左右されるものではありませんし、ツボはそもそも関係ありません。コリ(あるいはトリガーポイント)に当たるか否かに左右されることになります。
文献 )
The impact of patient expectations on outcomes in four randomized controlled trials of acupuncture in patients with chronic pain; Klaus Linde., et al., Pain 128 (2007) 264–271.