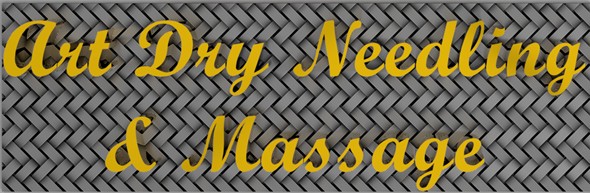顎関節症の鍼治療・マッサージ治療
総論
解剖学の世界では「哺乳類は物を噛む脊椎動物」という言葉もあるくらいで、生きることと噛むことは切り離せない関係です。ゆえに噛むことに関するトラブルは、単に栄養摂取という身体的な側面だけでなく精神面も含めた大きな影響を及ぼす場合があります。
顎関節症に限らず関節のトラブル全般に言えることですが、先天性のものでない限り、骨(関節軟骨)やその複合体である関節の異常はあくまでも結果としてそうなっているということで骨や関節そのものに原因があるわけではありません。骨は自ら位置を決めているわけではなく、関節を取り囲む筋肉や関節包・靭帯など(=軟部組織)が様々な方向から骨を引っ張り合った結果として位置が決まってきます。
顎関節は4つの筋肉が下顎の骨を釣っている状態で、それらが程よい張力でバランスされていれば動きもスムーズで痛みや異音も出ませんが、全体が過緊張を起こしたり特定の筋肉が筋短縮を起こすなどしてアンバランスになると関節症が起こってきます。
ですので治療も歯を削ったり骨を押したり引っ張ったりというのではなく、大元の原因になっている周囲の軟部組織、特に筋肉の過緊張や筋短縮を元に戻すことが必要です。
顎関節症の場合、マッサージであれば側頭筋や咬筋を治療できますし、鍼であればそれらに加えて深部の筋肉(外則翼突筋など)にも直接アプローチすることができるので上手くやれば鍼灸師が最も活躍できる場面の一つと言えます。
治療院を構えて驚いたことの一つに、顎関節症でお悩みの方がこんなに多くおいでになるのかということです。
当院には、主に口の開閉時の「痛み」や普段の「重だるさ」を何とかしたくてお見えになられるわけですが、それらは顎関節の部位に限らず、頭痛・顔面痛・耳の周りの不快感・首肩の痛み・のど~胸にかけての気持ち悪さなど広範囲に及ぶことが多い特徴があります。
痛みの程度も、あごの開閉時の痛みがあまりに強いため「気がおかしくなりそう…」と訴える方もおいでで摂食障害(痛くて食べられない、噛まずに摂取できる流動食のみ)を併発していることもあり、深刻な場合があります。
当院にお見えになる顎関節症の方の特徴として言えるのは、ほぼすべての患者様がそれまでにかなりの数の様々な治療・治療院を経験されてきているということです。(また、実際に治療に至らなくても、ずいぶん遠くの地方にお住まいの方からのお問い合わせもあり)この症状でお悩みの方が、どうにもならないまま長期間にわたり苦しんでいらっしゃることが分かります。
ただ、あまり無責任なことは書けませんが実際に治療をしてみるとほとんどの場合、予後は良い印象です。
症状
顎関節症は顎関節やその周囲の軟部組織に現れる痛みや障害の総称です。
代表的な症状は、1・あごが痛む「顎関節痛」、2・口が開かない「開口障害」、3・あごを動かすと音がする「顎関節雑音」です。この3つのうち1つ以上の症状がみられれば、顎関節症の可能性があります。
ただし、現在では症状が「顎関節雑音」だけの場合は不快かもしれませんが治療の必要はないとされています。とはされていますが…. 小さな音でしたら良いでしょうが、たまにゴキゴキ音がしている方おいでです。こうなるとやはり放っておくのは良くない気がします。中で骨・関節軟骨・関節円板の何かがぶつかっている音ですのでいずれ何か問題になりそうです。
症状がひどくなると顎関節だけにとどまらず、めまい、頭痛、首の痛み、肩こり、背中の痛み、腰痛、腕や指のしびれ、頭痛、耳や鼻の不快感や違和感など全身に症状が現れることもあると考えられています。実際にはどちらが先に始まったかは分からない場合が多いのではないでしょうか。首肩周りの硬さや痛さのせいで顎に力が入り出すこともあるでしょうし、同時に始まることもあるでしょう。
*関連症状・全身症状については科学的実証が十分ではない、という指摘もあります。(しかし、臨床現場では顎関節だけが問題だという方はほとんどいらっしゃらないですね。)
顎関節の構造
顎関節は、頭蓋骨(側頭骨)と下あごの骨(下顎骨)とをつないでいる関節です。
靱帯(じんたい)、腱、筋肉がこの関節を支え、あごを動かしています。
顎関節は、体にある関節の中でも最も複雑な関節の1つと言われ、蝶番のように開閉できるだけでなく、前後左右にずらすこともできます。
顎関節には、クッションの役割をする関節円板と呼ばれる高密度の繊維性組織があり、頭蓋骨と下顎骨が直接こすれ合わないようになっています。
開口時に下顎骨頭が関節円板を上手く越えられないと異音や開口制限、痛みの原因となります。
咀嚼筋は、側頭筋、咬筋、外側翼突筋、内側翼突筋の4つの筋肉で構成されます。
下図pic.1~pic.3参照(NETTER ネッター解剖学アトラス:南江堂より)
各咀嚼運動に関わる筋肉
閉口: 側頭筋、咬筋、内側翼突筋
開口: 外側翼突筋、(舌骨上筋群、舌骨下筋群)
前突: 外側翼突筋、
後退: 側頭筋、咬筋
側方(すりつぶし)運動: 同側の側頭筋、対側の翼突筋、咬筋
(ATLAS OF ANATOMY グラント解剖学図譜, p663より)
罹患の傾向
症状の軽重を問わなければ一生の間、二人に一人は経験すると言われているほど多くの方が経験します。
他の多くの関節症の如く女性に多い疾患ですが、年齢は10歳代後半から増加し、20~40歳代に多い症状です。
当院でもほとんどが女性患者様です。
顎関節症の分類
顎関節症のタイプには以下の5つがあります。
顎関節症I型:咀嚼筋障害 (咬むための筋肉の障害)
顎関節症II型:関節包・靱帯障害 (関節周囲の組織の障害)
顎関節症III型:関節円板障害 (関節の中の組織の障害)
顎関節症IV型:変形性関節症 (関節の形の変形があるもの)
顎関節症V型:I~IV型に該当しないもの
顎関節症の原因
実は、顎関節症の原因はまだ完全には解明されていませんが、一般的には歯並び・かみ合わせなどの咬合要因、歯ぎしり・食いしばりなどの行動要因、精神的ストレスなどの精神的要因、筋力・筋肉量や関節の構造的問題などの解剖的要因. . .などがあると考えられています。
従来は噛み合わせの悪さが主な原因だと考えられたこともありましたが、近年の研究で、噛み合わせは原因の一つに過ぎないという事が分かってきました。つまり、寄与因子が複数関与した結果生じる(多因子病因説)と考えられています。
このようなことから、“厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト”でも、
「顎関節症の原因は不明ですので、咬み合わせが悪いとか、体のバランスに問題があるとか、いかにも原因治療としている宣伝に安易に惑わされないことを勧めます。」
と注意喚起しています。
とはいえ、危険因子はある程度分かっていますので悪化を防ぐ保存療法や治療、日頃の行動の注意・改善もそれらに対して行っていくことになります。
特に、噛み締めのクセは大きな原因になっていることが指摘されています。
顎関節は、口を閉じていても上下の歯は接していないのが本来の姿ですが、顎関節症患者さんの多くは口を閉じているときに上下の歯が接している(噛んでいる)というクセを持っていることが報告されています。
この癖があると顎関節や筋肉に持続的な負担をかけることから、顎関節症を引き起こしやすくなります。
そしてこの癖を治すと、多くの方の症状が改善されることも明らかになっています。
とはいうものの…何かに集中したり、仕事で細かい文字を読む、PC画面と向かい合って作業する、などでは自然とあごに力が入りがちなので一度癖がつくと簡単に治すというわけにはいかないようです。また、寝ている最中の噛みしめや、歯ぎしりのような場合その癖を治すのはさらに難しくなりますね。このような場合噛みしめを止める効果とは別に歯を守るためにマウスピースは必須だと思います。男性の場合、嚙む力が相当強いので寝ている間に歯を割ってしまったり根元が欠けてしまうことがあります。
噛みしめ癖のある方は側頭筋などがとても硬くなるので緊張型頭痛を併発されていることが多いです。
顎関節症の治療(鍼治療以外)
以下の治療が一般的に行われていますが、それぞれの治療法の実績・証拠が乏しく、顎関節症の効果の高い治療方法が明確となっていないのが現状です。
薬物療法:顎の痛みを薬で抑えます。
理学療法:通電やマッサージで顎周辺の筋肉の緊張を解き、血流を改善しすることで痛みの軽減をします。
運動療法(リハビリ):ずれている関節円板を元に戻すための運動
スプリント療法:マウスピースを使用する方法。
手術、噛み合わせ治療
顎関節症に対する鍼治療・マッサージ治療
1型の顎関節症について
1型の顎関節症は、まさにこれらの筋膜・筋肉のコリを取り筋短縮を改善することが根本的な治療となるものです。
鍼は、咀嚼筋すべてに直接アプローチできるので、これらの筋肉の筋硬結・筋短縮を解消することが出来ます。
指で外から触れたりマッサージ治療ができるのは側頭筋と咬筋です。
鍼より細い指の人がいれば翼突筋もマッサージで狙えますがそんなことはありえないので、鍼はもっとも小さい侵襲性で直接効果を上げることが出来ます。
先に、顎関節症の罹患率は2人に1人という調査結果を挙げましたが、顎関節症の自覚症状がなくとも、肩こり・腰痛などのほとんどの患者様で咬筋・側頭筋に筋硬結が見られるので(一生の間で、臨界点を超えなければ発症しなかったというだけで)現代人は大多数の人が顎関節症の予備軍の状態にあるのではないかと思われます。
顎関節は下図 (pic.1) の通り、簡単に言うと、下あごを筋肉で吊っている状態です。ですので関連する筋肉のテンションで位置が決まります。そして、噛むときは一つの筋肉による単純な上下運動ではなくて主に4つの筋肉が関係し、かなり複雑な3次元的軌道を描きます。
生まれた時から何らかの異常があったり成長過程で骨の形状などに問題があれば別ですが、そうでなくて後からこの症状になったというときは4つの筋肉の緊張度合(バランス)の異常のせいで、下あご骨の位置がおかしくなったり、関節運動の軌道がおかしくなって関節円板が引っかかったり… が生じていると考えられるので、治療の進め方は、顎関節の位置や運動に強く関連する4つの筋肉を丁寧に治療していきコリや過緊張を取り除いていきます。
多くの場合、まず側頭筋(pic.2 の通り、一番大きな筋肉で、大きなものから小さなものまでコリがたくさん見つかることが多い)を丁寧に施術した段階でかなり症状軽減が見られます。咬筋にもたいていコリが見つかりますが側頭筋の方が顎関節症に悪さをしている度合が強い印象です。
(なぜかボトックス注射の治療を受ける方は咬筋にばかり受けることが多いようで、その場合、咬筋は萎縮してペタンコになっている反面、側頭筋が過剰に働かされて無茶苦茶凝っているという . . .これ、ほんとに大丈夫なのかな?余計、顎関節のバランス悪くならないかな?と内心思うことがあります。)
翼突筋( pic.3) のコリを取る治療は、「初めて受けた」と口々におっしゃるので行う治療院は少ないようですが、とても効果的です。なぜ治療しないのか謎です。
また、場合によってはあご以外に、噛みしめと同時に舌(~のどの前方)にも変な力が入り続けていると思われる方もあるのでその場合はオトガイ舌筋( pic.4 genioglossus muscle)に対する治療も行います。のど周りの筋肉と連動して力が入ることが癖になっていてあごの力が抜けない場合や、のどの違和感や不快感などがある場合、大変効果的です。この部位に関してはまず間違いなく「初めて受けた」と言われますがまあそうだろうと思います。
以上のような感じで、痛みに直接関連する部位をまず始めに見ていきますが、その後、様子を見ながら患者様のご希望に合わせて首・肩・頭・顔・のど・胸筋… と施術を進めていき、良い状態を確定していきます
2・3・4型の顎関節症について
そして、2型や3型、4型(4型についてはケガや先天性のものは除いて)についても、“関節症”である事についての一般的な原則、つまり、基本的にほとんどの関節症は、それを取り巻く筋肉・軟部組織の異常緊張やアンバランスが基礎にあるためアライメントが崩れたり関節を圧縮するような強い力がかかり続けたりすることによる(→ 筋肉内刺激法(IMS)について を参照)と考えられるので、1型以外の顎関節症に対しても、結局は、咀嚼に関連する筋肉の異常緊張や血行不良を丁寧に解消していくことがより根本的な治療法になると当院では考えています。
したがって、基本的に何型の顎関節症であっても関連する筋肉などの筋硬結を解消し筋緊張を解いていく作業を丁寧に行っていくことになります。
下図 pic.1: 咀嚼筋の作用する方向(図:プロメテウス 解剖学アトラス / 頭頚部・神経解剖 :医学書院より)
特に、側頭筋、咬筋、外側翼突筋の筋硬結を解消すると(内側翼突筋がどの程度関与しているのかは分かりません)顎を動かしたときの軽さと頭のスッキリした感じに驚かれる方が多いです。
(pic.1) 顎関節は主に4つの筋肉で下あごの骨を吊った状態。これらの筋肉の引っ張り具合によって下あごの骨の位置が決まる。

(pic.2) 側頭筋と咬筋(側頭筋は図でみるととても大きいが、実際に筋肉の厚みのある部分は狭い。コリは多くの場合放射状に存在しそれぞれ細い線状であるので細かく見つけて取っていく必要があります。うちわの骨みたいな感じですね。)

(pic3) (外側・内側)翼突筋。外側翼突筋はあごを前に出したり口を開くときに、内側翼突筋は閉じるときや食べ物をすりつぶすような動作のときに使います。

(pic.4) オトガイ舌筋:噛みしめと並行して、のどや舌に力が入ってしまっている方が多い。