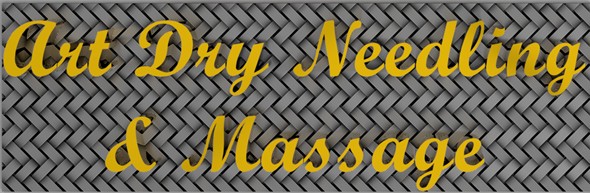「筋肉の血液循環」と「コリ」とその治療について
一般に鍼灸マッサージの治療の対象となっているのは筋肉(1~数cm)および筋束(数mm幅の単位)レベルです。
ここではまず「骨格筋の血液循環」の様子についてご紹介します。凝っていない正常な筋肉の様子、つまり治療によって目指すべき姿です。
そして「コリができる条件」を簡単に説明した後、それが「治療でどのように変化していくのか」を説明いたします。
骨格筋の筋駅循環
筋肉の基本的な作用と構造の説明のコンテンツでご紹介しました通り、筋線維(筋肉の細胞)の一本一本に血管が分布しています。
図1 (骨~筋繊維まで)

(出典:Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Third Edition, p45, (Travell, Simons& Simons)
図2 (筋繊維の部分にフォーカスした図)

(出典: 『やさしい自律神経生理学 生命を支える仕組み』 鈴木ほか, p.114.)
骨格筋に分布する血管は、神経と一緒に骨格筋の線維束の内部に入り込み、多数の毛細血管に枝分かれして、すべての筋線維に分布しています。隣り合った毛細血管どうしは、筋線維を横切る血管によって互いに吻合し、網目構造を作っています。このため、仮に毛細血管の一部がふさがっても、血液は迂回して栄養や老廃物を運搬することができます。
意外なことに、安静時の骨格筋血流は、筋の重量に比べると少なく、安静時の心拍出量が約6リットル/分とすると、体重の2-3%の重さを持つ脳へは0.75リットル/分の血流が供給されるのに対し、体重の45-50%を占めるにもかかわらず骨格筋に対してはたったの1.2リットル/分の血流が供給されるにすぎません。
これは筋に分布する血管の緊張が安静時に高いことによると言われています。
したがって、その緊張がさらに高くなれば血流はとても少なくなってしまい、長時間に及べば正常に機能できなくます。
この筋肉内の血管の緊張の具合をコントロールしているのは交感神経です(交感神経性の血管収縮神経)。
疲労や精神的ストレスなどで精神的緊張が高まったり、痛みなどで交感神経が興奮状態にあると筋肉に通っている血管が収縮することになるので筋肉への血流が減少します。(=アドレナリン作動性血管収縮。この神経の活動が高まると神経の末端からノルアドレナリンが放出されて、血管平滑筋のα受容体に作用し、血管を収縮させることになります。)
*血管収縮が日常で活躍する場面:
→ 座位や臥位から立ち上がった時に、上半身への血流が不足(=立ちくらみ)しないように下半身の血管を収縮させる、などの場面で延髄の循環中枢と連携し血液配分を調整しています。
その一方で、筋肉内の血管に交感神経性の血管拡張神経(コリン作動性の血管拡張神経)が存在することがネコを対象とした研究から明らかにされています。
この神経はトーヌスは有せず、神経の興奮に応じ末端からアセチルコリンを放出し、血管を拡張させます。
また、血管拡張神経から放出されるアセチルコリンは、アドレナリン作動性血管収縮神経末端でのノルアドレナリン放出を抑制し、血管収縮を抑えることで血管拡張効果を高めていると考えられています。血管収縮にも拡張にも交感神経が関係しているということで、こういった、ブレーキをかけながら同時にアクセルを踏むようなことをやっているところが人体の不思議というか興味深いところです。
血管拡張神経は、運動時などの急激な筋血流増加を必要とする場面で働くと考えられています。そのような結果、安静時に1・2リットル/分だった血流は運動時には約10倍(12.5リットル/分)にも達します。
運動時には骨格筋(と脳血管・心臓冠血管)以外の多くの部位においては細動脈を収縮させて血流を減少させます。運動能力の向上と、(戦闘において)ケガをした時の出血を最小限に抑える意味もあると考えられています。
運動時の骨格筋の血流増加は、主に乳酸・カリウムイオン・などの代謝産物による局所性の血管拡張作用によります。また、これらの物質がアドレナリン性血管収縮神経の末端に作用し、ノルアドレナリンの放出を抑制、あるいはα受容体の感受性を減弱させることなども骨格筋の筋血流増加を助けます。
*筋肉への遠心性の交感神経線維はC線維で、筋肉組織の血管壁の平滑筋に分布しています。ほとんどは血管収縮性の機能を有し、約10%がコリン作動性の血管拡張ニューロンと考えられています。(Rowell, 1981.など)
コリのできる条件
運動時のように十分な血液補給がなされていれば、「個々人の筋肉の能力の限界に近いような余程の高強度」あるいは「弱い力でも長時間の使用」でない限りコリに至ることはありません。
「個々人の筋肉の能力の限界に近いような高強度の使用」によりコリに至るのはわかりやすいですが、「弱い力でも長時間の使用」によりコリに至るというのは少しわかりにくいかもしれません。「同じ姿勢で長時間過ごす」などのように筋肉に力が入りっぱなしになっている状況は、確かに発揮する力は弱いですが図2で分かるように筋収縮により筋繊維同士がお互いに締め付け合う状態になるので、筋線維間の毛細血管が継続的に押しつぶされた状態になります。これにより血流が途絶えて栄養不足、老廃物の蓄積、エネルギー(ATP)の枯渇などが生じ、収縮時に使用されたカルシウムイオンの回収ができず筋肉が弛緩できなくなるため(アクチンとミオシンがはまり込んだままロックされた状態)筋硬結(コリ)に至ると考えられます。詳しくはコリの正体と生成原因・メカニズムをご参照ください。
コリが治療により変化する様子
実際の治療との関連でいうと、筋肉はまんべんなく凝るわけではないので一部の筋束が主な治療の対象になります。
例えば、仮に僧帽筋が3000本の筋線維(←本当はもっと桁違いに多いですが数が大きすぎて分かりにくくなるので)から成り立っているとした場合、3000本が一様にまるまる凝るわけではなく、その中で100本程度が固まってコリを作っているという具合です。これを素早く見つけて治療していくのが日々の臨床現場で行われていることです。正常な2900本に対して鍼・マッサージをしても気持ちは良いかもしれませんがコリやそれに起因する痛みは解消しません。
始めは大きければcm単位の幅で硬結(こり)が触知されたりしますが(たいてい小指や薬指くらいの太さ)
段々ほぐれてくると5mmくらいの硬結が残り、
さらにほぐれてくると2mmくらいの芯の部分が残ったりします。太かったコリの束がほぐれて細くなっていく過程は、口の中で飴が溶けてだんだん小さくなる様子、あるいは冷凍庫から出した氷が室温でだんだん解けて小さくなっていく様子に似ています。
*若かったり、コリの年季が短ければ一気に解けることがありますが、慢性化したコリは鍼が当たるたびに少しずつ小さくなっていくのを繰り返して消えていきます。この小さくなっていくスピードは年齢・コリの程度・体質(ほぐれやすさ)などによって異なります。
たまに糸のような細いコリが残ります。この細さになると当てるのが結構難しくなりますが、そんなに小さくなっても悪ければしっかり響きが出ます。(コリの大きさと悪さ比例しないことが分かります。)
トリガーポイント療法などでトリガーポイント好発部位が紹介されていたり、経穴が決められていることなどから分かるように、人が凝る場所や悪い(反応が出る)場所はだいたい決まっています。
ゲートコントロール理論で有名なR. メルザックが、痛みを取るためのトリガーポイントと経穴を丹念に調べた結果、71%程度、重なっている、と報告(Melzack,R.,1977)しています。
しかし、個人ごとにコリや反応点の位置や重要度に違いがありますので、治療の際には、症状をうかがってある程度あたりを付けながら治療の優先順位や、細かく見る範囲と程度を決めていくという事になります。
☞ (Melzac.1977) 『Trigger points and acupuncture points for pain: correlations and implications』
参考文献
『筋肉学入門 ヒトはなぜトレーニングが必要なのか』; 石井直方, 講談社, 2009.
『シンプル生理学』; 貴邑冨久子, 根来英雄, 南江堂, 2016.
『やさしい自律神経生理学 生命を支える仕組み』; 鈴木郁子, 中外医学社, 2015.
『生理学』; 佐藤優子, 佐藤昭夫, 医歯薬出版株式会社, 2003.
Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Third Edition, p45, (Travell, Simons& Simons)
『Trigger points and acupuncture points for pain: correlations and implications』; Melzak, R., Stillwell, D.M., & Fox, E. J., Pain, 3, 3-23.,1977.
『体性-自律神経反射の生理学』; 佐藤昭夫他、丸善出版、2012.