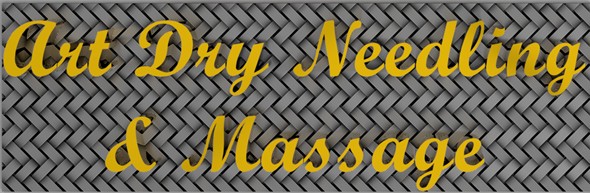四十肩・五十肩の治療
ほとんどの場合、四十代以降で生じるので老化が一つの原因と考えられますが、それ以上の直接的原因については一般的に「不明」とされています。
成人以降の方を触診すると、四十肩・五十肩でない方でも、ほとんど例外なくローテーターカフと呼ばれる筋肉群(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)に筋硬結及びかなりの圧痛が見られます。
実際には10代の方でも結構硬くなっているものなので、腕をぶら下げて筋肉と靭帯などで釣っている人体の構造上、硬結・短縮を起こすのは仕方ないことなのかもしれません。
特に経産婦さんは授乳時の姿勢のせいか左側の上肢に関連する筋群に強いコリができたまま何年~何十年と経っていることが多いです。実際海外でもおよそ3分の2の女性が左側で抱っこするという論文が出ています。☞Handedness and sex effects on lateral biases in human cradling: Three meta-analyses)
特に下図で示される棘上筋と小円筋は後述の通り要注意で当院が重視している筋肉です。
これらの筋肉(に加えて、大円筋・三角筋の後部繊維なども加わり)の硬結・短縮により肩関節のアライメント(=関節の機能を十分発揮できるような最適な位置関係のこと)が狂ったり、ある方向への引っ張りが継続することで関節包や筋膜への物理的ストレスが蓄積しているところに、何らかのきっかけ(上にあるものを取ろうと腕を上げた・荷物を持ち上げた、ひねりの力が加わった、など)が引き金となり発症に至ると考えられます。
つまり、肩先で出ている痛みや炎症の症状は、長年の蓄積によるローテーターカフの硬結・短縮が原因となって生じた結果に過ぎないと考えられるので、まずはローテーターカフやその周囲の筋肉の凝りを丁寧に取っていくことが重要です。その後、関連する周囲の筋肉の凝りを取っていきます。
この辺りのメカニズムは実証できないので科学的な根拠に基づくものではありませんが、当院での臨床経験上はローテーターカフと周囲(首・肩・腕など)の筋群を丁寧に治療することでかなり改善されているので方向性としては間違っていないと考えています。
拘縮を防ぐために運動が勧められますが、硬くなり筋短縮を起こしていることを無視して無理に動かすと余計に組織を傷めるだけなので、順序としてはコリを解消してから筋や筋膜・関節包などの短縮を改善するために可動域訓練・運動を行うべきです。
*急性期で炎症がひどい場合は(肩先を触ると熱い)その局所への直接の刺鍼は避けます。ただ、初期のうちに小円筋などのコリをしっかりとることに成功できれば四十肩・五十肩で苦しむ期間は圧倒的に短くて済みます。このあたりのジレンマが治療を難しくしている一つの理由です。
小円筋は図で見ると大きく見えますが、実際には小さな筋肉で、多くの場合直径5ミリくらいの硬いコリのラインが見つかります。この筋肉にひどいコリ・筋短縮があるという事は、上腕骨を外旋させたり斜下方に引っ張り続けることになります。
棘上筋で頻繁に生じる腱損傷などは、腕の重みに加えて、小円筋の筋短縮により下方に引っ張り続けられ続けた結果として生じていると考えられます。
小円筋はとても小さなコリにもかかわらず固まって密度が高くなっていると極細鍼でも無茶苦茶に響きますのでまずはマッサージである程度ほぐしてから鍼治療が良いと思われます。この5mmのコリのラインを丁寧に刺鍼していけば間違いなくほぐれます。正確な鍼操作が求められる場面です。
棘上筋は決して小さい筋肉という訳ではないので当たらないという事は考えにくいですが、幅(面積)がある分、その中のどのラインに負担が多くかかって悪さが溜まっているかを見極める必要があるのと、それがどの深さにあるのか(必要な刺鍼の深さ)についての理解と、筋肉に当たった後に効果的な鍼操作が出来るかどうかが重要です。
比較的単純な症状である肩こりと違って、四十肩・五十肩の治療は、首こり治療などのように施術者が勝ちパターンを持っているかどうかで得られる結果がまるで違うのではないかと考えます。
初期であればあるほど治療による効果が出やすいです。

(図:『Netter 解剖学アトラス』, F.H.Netter, 訳 相磯貞和, 南江堂.より)